殺したら負け。最近の謀略スパイアクション
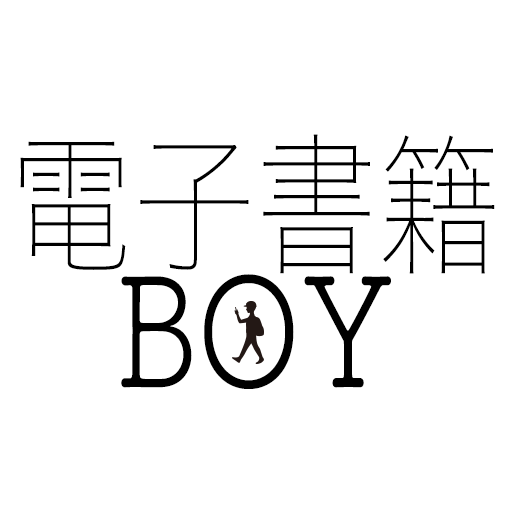
名作スパイアクション
殺人許可証なぞ存在しない!
犯罪がまかり通る世であってはならない。あまねく人々を貫く誠の真理ではなかろうか。しかし、それが通用してしまう困った世界がある。それは、スパイ映画の世界である。スパイは目立たぬように、国家や軍事上の最重要機密を、相手に悟らぬように盗みとることが任務の主たるところだが、破壊工作や暗殺も時として仕事になる。その面にフォーカスがあたり過ぎる嫌いがあるのは、これまで映画等で取り上げられることが多かったからだろうか。もちろん、その理由はよくわかる。映画会社にしてみれば、派手で絵として映えるスパイアクションは映画にもってこいだ。拳銃が鳴り響き、爆薬の轟音が耳をつんざく。謀略を重ねる心理戦は見ている人を飽きさせない。そして、人が死ぬことで、作品にスリルが生まれる。
ただ、いつも疑問だったのは、現実世界のスパイはそんなこと本当にしているのか、ということだ。スパイ作品の金字塔と言えば、イアン・フレミングの『007シリーズ』だろう。その中に出てくる主役ジェームズ・ボンドは、殺しに殺しまくる。英国のスパイで、殺人許可証なるものを政府から渡されているらしい。顔も売れていて、大体各国に友人がいたりする。スパイとして顔が割れすぎているというのはどうなんだという気がしなくてはないが、彼は縦横無尽に世界を飛び回る。スパイとして。
暗殺者として、スパイとして、堂々と敵勢力の中枢で敵を屠り去るのは、確かに偉業なのだが、そんなことを毎度の如くできるのがそもそも摩訶不思議である。セキュリティも年々強固になっていくだろう。そして、ただでさえ、顔の売れているスパイ。すぐに空港とか街中で、御用になるのではないか。
昔の作品はとにかくスパイが派手に描かれている
ロバート・ラドラムの『暗殺者』は映画『ボーン・アイデンティティーシリーズ』の原作である。とにかく主人公が強すぎたり、スパイの嗅覚に優れていたりと現実離れしている。標的が世界のどこにいるか、勘でわかってしまうのだ。
フォーサイスの『ジャッカルの日』も名作に違いないが、国際社会を逃げる犯人をいつまでたっても捕まえられないのは、スリルやサスペンスを超えて異常なユーモアを現代人の感覚で読むと感じてしまう。
現実世界のスパイは目立たないことが仕事
スパイの本懐は情報を持ち帰ったり、敵に誤情報を与え混乱を生じさせることだろう。裏工作や暗殺・破壊工作はリスクが高く、効果が見込めないため、二の次なのではないだろうか。
007シリーズ、その他の作品はエンタメに昇華させるために、スパイの持つ側面の華やかで活動的な部分をデフォルメしているのだ。
つまり、現実のスパイ活動を描いているわけではない。本当のスパイとは、きっと007では似ても似つかない存在だろう。目立たなくて、ダサくて、暗くて、英国紳士ではなくて、女にモテない。これは私の勝手な決めつけに過ぎないが、目立たないというのは、一つの大切な要素な気がする。
そこに着目した、本格スパイ小説がある。
柳広司による『ジョーカー・ゲームシリーズ』だ。この作品の中でスパイ養成機関が出てくるがそこで徹底して教えられるのが「殺しはご法度」というルールだ。理由は簡単で、人が死ぬというのは不自然なことであり、そこから全てがご破算、スパイ計画そのものが破綻するというのが理由らしい。人は死なないがスリリングな展開はきちっと用意されているので、従来のスパイアクションが好きな人でも楽しめる作品となっている。
この本に書かれている優秀この上ないスパイ達が、現実世界のスパイだとはもちろん思えないものの、目立たないことを第一とするのは新しい風だとも思う。
近年の世界的ベストセラーに間抜けな諜報チームが出てくる
とは言え、やはり派手なストーリーに人々は惹かれるものだ。物語にスリリングを与えるために、スパイ役を設けて、殺しを演出する、というのは物語作品全般に見られる、王道の演出方法だろう。エンタメの常套手段と言っていい。
スウェーデン発のベストセラー『ミレニアムシリーズ』にも、実はスパイが出てくる。主人公の一人、リスベット・サランデルの父親が実はソ連のスパイだったという設定だ。その父親をめぐる騒動を描いたのが第3巻だ。そこにはスウェーデンの国家的スキャンダルの原因ともなるべき、諜報集団が関わっている。個人的には、このチームが実に愉快なのだ。普通、スパイといえば、怜悧冷徹かつ狡猾で、常に相手の裏をかいて行動し、戦果を得るものだと思うだろう。ところが、ここに出てくるスパイチームは素人なような動きで、あまり主人公陣営を苦しめない。常に後手にまわってしまい、ついには壊滅してしまう。そんなチームを率いるのは透析を受けながら、老害として、頭目に君臨する老人なのだが、そんな設定も、私にはやり過ぎたウケ狙いに映った。実際、3巻冒頭で、スパイがやってはならない『殺し』を仕出かしてしまうのだが、この小説ではそうなった場合の、現実的な警察やマスコミや行政の処理といったものが淡々と描かれているのかもしれない。(私はそれを、風刺にも似た、ブラックユーモアと受け取った)
-
前の記事

「カズオ・イシグロ」祝ノーベル賞! 電子書籍書店の対応調べ 2017.10.08
-
次の記事
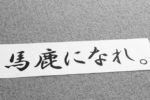
いや、これクソだろw バカミスの世界 2017.10.10




